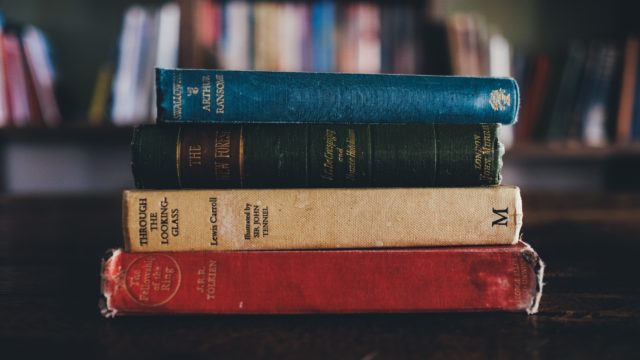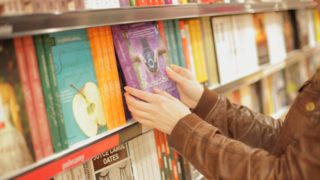前回記事「芥川賞作家か直木賞作家かライトノベル作家のいずれをめざすべきか」では不肖ダイナレイはライトノベル作家をおすすめする理由を書きましたが、まず第一に芥川賞作家をめざすのはおすすめしないと述べました。
理由として芥川賞作家は儲からないことを上げましたが、その主な根拠となったのが今回ご紹介する「ワセダ大学小説教室 天気の好い日は小説を書こう」三田誠広(集英社文庫・2000)という本です。
(補足として小説家になろう本を上梓した作家や編集者は、ほぼ例外なく芥川賞作家は儲からないと言っていますw)
ちなみに前々回記事「小説家になる人は小説家になりたいと言う前に書きはじめているという事実」の根拠になっているのもこの本です。(もちろん、他の作家さんのインタビュー記事も根拠になってます)
また、専業小説家をめざすより兼業が良いのではないかとおすすめするに至った根拠もこの本に拠(よ)っています。
何しろ芥川賞をとった有名な作家先生でもいまだに会社勤めをつづけている人がたくさんいると教えてくれたのがこの本です。
衝撃でした……!
そんなに儲からないのかと……。
当時のダイナレイは芥川賞とったら小説家の勝ち組だと思っていたので、まさかその辺のフリーター並の収入しか得られないとは夢にも思いませんでしたw
世間で芥川賞を知らない人なんていないじゃないですか?
文學界新人賞やすばる文学賞は知らなくても、芥川賞と直木賞は知っています。
それなのに、フリーターとたいして変わらない年収なんて、そりゃ専業では生活できませんわな。
というわけで、「ワセダ大学小説教室 天気の好い日は小説を書こう」を読んでおけば純文学作家をめざすあなたにはとても参考になるはずです。
ちなみにワセダ大学小説教室は3部作でして、「天気の好い日には小説を書こう」「深くておいしい小説の書き方」「書く前に読もう超明解文学史」の3冊が集英社文庫から出ています。
3冊で一作品と思って全部読んだ方がいいです。
文学というモノの理解が格段に深まります。
とてもわかりやすく明解に書いてあるので、ふだん本を読まない方でもわりと読みやすい本だと思いますよ。
なので、文学について知りたい人や、純文学は敬遠したいけど小説家になりたいお星さま方にもおすすめします☆
ホントに、勉強になりますよ。
全国の中学高校生の副読本にしたいくらいです。(そういう本でないとわたし紹介しませんからねw)
芥川賞作家 三田誠広先生の簡単な経歴
三田誠広(みた・まさひろ)
1948年6月18日生まれ
大阪府出身
高校2年生(17歳)の時、1年間休学して「Mの世界」を書き、文藝学生小説コンクール佳作入選を果たして文壇デビュー
早稲田大学第一文学部演劇専修卒業
広告プロダクションにてサラリーマン
ダイナレイが生まれた1977年に「僕って何」で芥川賞を受賞
1988年から早稲田大学で教鞭をとる
現在は早稲田大学客員教授を経て武蔵野大学教授
日本文藝家協会副理事長
歴史時代作家クラブ会員
もっと詳しく知りたい方はWikipediaで調べてください。
リサーチも小説家修業の一環ですw
それでは、三田誠広先生の文学に対する熱い想いを垣間見てみましょう。
天気の好い日は小説を書こう
本のタイトルにもなっていますが、プロローグのタイトルです。
ちょっと不思議な一文ですよね。
ふつうは「天気の好い日は外に出よう」とか、「天気の好い日は布団を干そう」とか、そういう文脈が活きてくると思うのですが。
「天気の好い日は小説を書こう」???
頭の中で、はてなマークが飛び交います。
むしろ「天気の悪い日は小説を書こう」でいいのでは?と思ってしまいます。
雨の日は外に出たくないですから、格好の読書&ライティング日和ですよね。
――三田先生があえてこのタイトルにした理由が知りたいですよね?
結論から言います。
読者に提案したかったのです。
「天気の好い日は小説を書こう」って!
うっとうしい梅雨空のもとで、よい小説は書けないよって。
自分は「孤独だ」なんて書いたらその他大勢の仲間入りだよって。
暗い人間はたくさんいて、暗さは個性でも特権でもないから、その暗さそのものは取り立てて人に言うべきモノではないんだよって。
以下に引用します。
もう一度くり返すけれども、小説は、書き手の自己満足の手段であってはならないし、現実から逃避するためのシェルターであってはならない。暗く沈み込んだ状態で書き始めたのでは、よいものは書けない。
小説を書くためには、ある種の気分の昂揚が必要である。小説とは過激で、野心的なものだ。読み手にコミットする積極性が必要だ。意欲に燃え、力強く、そして明るく楽しく書いていくためには、何よりも、いい気分で書かなければならない。
「ワセダ大学小説教室 天気の好い日は小説を書こう」三田誠広(集英社文庫・2000)
まさか、純文学の作家さんから「明るく楽しく書いていく」ことを提案されようとは!
いい気分で書くために「天気の好い日は小説を書こう」なんですよ!!
これぞ正しく青天の霹靂~!!ってなもんですw
あんなに「暗い」が代名詞の純文学畑の方がこのようにおっしゃるとは……!!
正直、純文学を書くにあたって明るい要素があるなんて思ってもみなかったダイナレイですw
やっぱり純文学といえば太宰治の「人間失格」や芥川龍之介「羅生門」のイメージがあるので、独りウツウツと人間の暗黒面を書いているイメージしかありません。
あなたが中学高校で習ってきた文学史上の名作もほとんどジメジメ暗いはずです。
少なくとも、読後、「はぁ~楽しかった!」っていう爽快な気分は1㎜たりとも味わえない作品ばかりだったと思います。
つまりこれは、書くときの作家の心構えの話で、できあがってくる作品のことではないんですね。
ここ誤解すると大変です。
例えば、人によっては村上春樹の「風の歌を聴け」は明るい純文学小説に分類するかもしれませんが、ライトノベルを読む世代から見れば十分暗いですよね。
ポップでライトでカラッとしてるって言うけど、十分根暗ですよね。
全体的なトーンがもう暗いですからね。
けれども、確かに「天気の好いときに書いたんだろうなぁ」って思うくらいにはカラッと仕上がっています。
これが大事なんですね。
「読み手にコミットする」には、自分が暗く沈んでいたらダメなんですよ。
読み手が受け取れないくらい独りよがりにベトベトしちゃうので。
まあ、そもそも明るいも暗いも主観的な要素なのでとても判断が難しいのですが、純文学の作品はその内包するテーマから言って、どうしたって明るさを維持できません。
だって写実主義な上、テーマが深いんですから。
まぁ、芸術ってそういうものですよね?
かろうじて舞城王太郎「阿修羅ガール」(新潮文庫)あたりは明るい純文学に分類してもいいかなとは思いますが、舞城先生は純文学作家と大衆作家のちょうど中間のような方ですから、イレギュラーなアウトローです。
「阿修羅ガール」の表紙はもろマンガ系イラストで、これはライトノベルじゃないの?ってくらい文章もライトでポップです。
この小説「どうみても純文学作品じゃないでしょ!?」っていうレベルでライトです。
「純文学作品はちょっとなぁ」という方でも、この作品は読めると思います。
三島由紀夫賞を受賞してるんですよ。(三島由紀夫は言わずと知れた純文学作家で、三島賞は権威ある純文学の賞です)
要するに、ライトノベル的構造だから明るさを維持できるんですよ。
けれど、この作品だって読んでもらったらわかりますが、読後感は暗いと思います。
ポップでライトだけど暗黒なんです。どす黒いです。中身が。
これが純文学なんですよねぇ。
というわけで、「天気の好い日は小説を書こう」!
でも、天気が悪くても小説は書くべきですw
補足:3冊目のエピローグのタイトルは「どしゃぶりの中でも小説を書こう」ですw
小説がスラスラ書ける黄金の秘訣
うわ~お、すっごい読みたいタイトルですよね!
「ワセダ大学小説教室」シリーズはその名の通り、三田先生が早稲田大学の文芸科で「小説創作」の演習を担当した際の講義(全18回)をほとんどそのまま収録しています。
1冊目に収録されているのは最初の6講義で、基礎編の最終回(第6回)のタイトルが「小説がスラスラ書ける黄金の秘訣」です。
うん、これね、久しぶりに読み返してみて思ったのですが、
タイトル詐欺じゃね?(小声)
真剣に小説家をめざすあなたならこの本は買うと思うのでネタばらししますが、
小説を書くのに実は秘訣はない
って、最後の小見出しに書いてあります。
やっぱりタイトル詐欺w
以下は先生の言い訳です。
もともと、小説を書くのに、秘訣などはないのですね。
ただ、基礎をまったく知らずに書き始めると、試行錯誤しているうちに、どんどん齢(とし)をとってしまう。小説を書くのにもっとも必要なのは、みずみずしい感性、といったものですが、技術的なものを学んでいる間に齢をとってしまって、感性のみずみずしさが失われてしまう、ということになってしまうと困りますから、とりあえず基礎を学んでいただくために、この本を出すことにしたのです。
「ワセダ大学小説教室 天気の好い日は小説を書こう」三田誠広(集英社文庫・2000)
だそうです。
ダイナレイの現状を予言するかのようなことをおっしゃってますね……あたくしは何を学んでいたのでしょうか……(泣)
きっと18年前のダイナレイはここを斜め読みですっ飛ばしたんでしょうね。
というか、純文学作家になる気はサラサラなかったので、我がコトとして受け止めなかったんでしょう。
でも還暦過ぎで受賞した芥川賞作家だっているんですから、年齢は関係ないって今こそ開き直って反論したいと思います!(キッパリ)
みずみずしい感性なんてなくたって小説は書けます!(破れかぶれの雄叫びw)
まぁ、あるに超したことはないですが……(そこは否定しません)
まとめ
小説というのは、他者へのメッセージであり、想像力を媒介とした魂と魂のコミュニケーションの場なのだ。
というのが作家、三田誠広の小説観です。
「どうしても書きたい、書かねばならぬ、という内的衝動が必要」ともおっしゃってます。
それから、「良質の文学はあまり売れない」ともおっしゃってますねw
やっぱり?って感じですがww
この後にまだ2冊つづくので、あと2記事つづきます。
三田先生曰く、1冊目のこの本は「小説の書き方の基礎の基礎の基礎」で、
「誰でも小説が書ける」といった感じでお話ししたつもりらしいです。
イヤイヤ、ウソおっしゃい~。
小説は努力すれば書けるというものではないとか、書きたい衝動が必要とか何気にハードルの高いことばかり言っていますからね?
そしてさらに2冊目は上級篇だそうです。
「誰でも書けるような小説を書いていてもしようがない」というところからお話を始めるそうです。
手厳しい~なぁ~。
「深くておいしい小説」を書くためには、「理論」が必要。
これにはダイナレイも全面的に同意します。
要するにこのブログで取り上げている構造論のお話ですね。
「面白い小説を書くにはどうしたらいいのか」を学びたい方は、ぜひ次回記事もご覧ください。