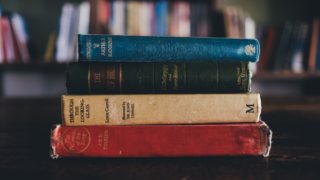こんにちは! まったり読み人ダイナレイです。
ではでは、いよいよ小説の書き方のルールを、たとえあなたがまったく小説を書いたことのない初心者さんであったとしてもわかるように、かみ砕いて順番に説明していきたいと思います。
まずは、あらすじ編です。
一般的に小説というのは、突如、天から降ってきたインスピレーションによって作家が一心不乱に書き上げるもののようなイメージを持たれがちです。
幻想ですw
一見すると、何気なく書き進められたかのように見えても、するする読めてしまう小説ほど作家は時間をかけて練りに練って書いていたりします。
そこには熟練の技があります。
「技」と言うからには根底には一定のルールがあります。
ダイナレイラボではその一定のルールを初心者向けにかみ砕いて明らかにしていきますので、ぜひ楽しみにしていてください。
まずは、初心者でも10分であらすじが書けるようになりましょう!
あらすじは小説における地図のようなものです。
これからあなたが一度も行ったことのない目的地に向かおうという時に、地図は必須アイテムですよね?
また、新人賞などの応募にも必ずあらすじ(概便)は必要なので、小説家をめざすのなら、まずはあらすじが書けなくてはなりません。
・小説は好きで、いっぱい読んだけれど、いざ自分で書こうと思ったら何から書いたらいいのかわからない。
・まったく何もイメージが湧かないけれど、とにかく一通り小説を書けるようになりたい。
そんなあなたも、これさえ読めば小説のあらすじをたったの10分で書き上げられるようになります!
読み終わったら即行でアイテムを召喚していることでしょう~w
小説の書き方のルールを初心者にもわかるようにマニュアル化
さて、小説を書くには熟練の「技」があると言いました。
「技」があるからには「ルール」があります。
「ルール」というものはその性質上、「マニュアル化」できるものです。
どうですか? こう聞くと安心しませんか?
小説の書き方もある程度までは技術的なトレーニングで習熟することができます。
つまり、誰にでも小説は書けるんです!
小説を書く場合に、初心者の多くがつまずく原因が、実はこの技術的な基礎トレーニングを経ていないことにあるのです。
才能のあるなしの問題ではないのです。
絵を描くのにはデッサンのトレーニングが必要ですよね?
歌を歌うのだって、まずはボイストレーニング(発声練習)からはじめます。
スポーツもいきなり試合に挑む前に、基礎的なトレーニングを積みますよね。
なのに、小説になるといきなり書きだそうとしてしまいます。
そして「書けない」「どうやって書いたらいいかわからない」となってしまいます。
あたりまえですよねw
確かに、どなたでも基本的な国語力は持っています。文章は書けます。だから勘違いしやすいんです。
国語的な文章技術は最後の最後でいいのです。絵画におけるデッサン力のように、書いて身につけるしかないんです。これこそ量が質に転化する最たるモノですので。
文章技術を追及するのは、最後にしましょう。それこそ誰にでもできる技術的トレーニングだからです。
それよりも優先して伸ばさなければならない能力があります。
なぜなら、ただ文章を書いただけでは小説にはならないからです。
小説に必要なもの。
それは、物語(ストーリー)です。
プラス、独自の切り口(構成)が必要です。
詳しいことは後述しますが、物語には同一のパターンがあります。その、同じパターン、同じ構造をいかに人とは違う切り口で再構成して独自性を出すかがプロ作家の腕の見せ所になるわけです。
ですから、物語には構成力が必要になってくるんです。
小説家になりたい初心者がまず身につけるべき力は、「物語力」です!!
物語構造(ストーリー)+ 物語構成(切り口)= 物語力(ストーリーテリング)
※カッコの中身はわかりやすく表現しているだけで、訳語ではありません。あしからず。
ちなみに、いわゆる純文学といわれる文芸作品には「物語がない」作品もあります。
それは、芥川龍之介や三島由紀夫が求めた、純粋に文章の芸術性を極める文学作品で、そこに起承転結(ストーリー)やらオチやらあってはならんのです。
これは文学をどのように定義するかにもよるのですが、ダイナレイラボではそのような小説は扱いません。
なぜなら、ごく一般的にいって物語のない小説はウケないですし、小説家になりたいあなたも、そのような芸術作品を書きたいわけではないと思いますので。
ですから、ダイナレイラボでは物語のある小説を推奨していきます。
つまり、純文学は脇に置いといて、エンターテインメント小説またはライトノベルを書くための技術に特化して解説していきますね。
では、肝心の物語力を身につけるにはどうしたらよいのでしょうか?
物語の文法を学ぼう!ゲームのように物語をつくる方法
もし、あなたが過去にいわゆる「小説家になろう」系の本を一冊でも読んだことがあったなら、おそらく小説家をめざすこと自体をやめてしまっていただろう確率は99.9999%以上です。
それくらい小説家修業の王道は、面倒で時間がかかります。
日ごろ本を読む習慣がない人なら、余裕で10年は覚悟しないといけません。本好きでも最低3年はかかります。(作家先生たちの持論)
実際、ダイナレイも小説家の道を志してすでに25年経ちましたが、正攻法で小説家になれる気はまったくいたしません。ぜんぜん修業しなかったのですからあたりまえですがw
(子育てと家事で物理的な時間が取れなかったというのは言い訳ですよ、ええ……)
「修業」という響きから、何やらイヤ~な雰囲気が漂ってくるように、とにかく王道はつまらないんですよ。
つ・ま・ら・な・い・の!
名作をひたすら音読するだの写経するだの、苦行以外の何ものでもないです。(キッパリ)
なので、もしダイナレイがプロの小説家をめざすなら、板前修業や噺家修業のように10年住み込みの弟子入り修業ではなく、1年で寿司の握りを教えてくれて、仲間ができて、独立開業まで支援してくれる寿司専門学校(実在します)のような学び屋を選びまっす!
あなたもそうではありませんか?
とういことで、前置きが長くなってしまいましたが、本題です。
物語の基礎文法は3つ「行って帰る」「難題→解決」「欠如→回復」
さて、物語の基礎文法は3つしかないと聞いて、そんなわけないと思ったあなた。
もちろん、世の中の物語には様々な種類、バリエーションがあります。
ですが、基礎というのは、家の土台と一緒で、そんなに何種類もいりません。どっしりと揺るがない土台があればいいんです。
物語の基礎文法3つ
1.「行って帰る」物語
2.「難題を解決する」物語
3.「欠如を回復する」物語
1.「行って帰る」物語
物語が発動するには、まず安全な日常の外に出なくてはなりません。
なぜなら、日常は日々の生活の積み重ねであり、毎日同じコトのくり返しです。誰かに伝えたいと思ったとしても、その誰かもほぼ同じ体験をしているので、「ああそうなの。わたしもよ」と返ってくるだけで、何の驚きも新鮮味もないからです。
(もちろん、この日常に異なる視点を取り入れて違う景色を垣間見せる文学作品もありますが、先に述べたようにここでは取り扱いません。)
よ~く思い出してみてください。小さい頃に読み聞かせてもらった昔話や童話の数々。
『桃太郎』『浦島太郎』『シンデレラ』『親指姫』『白雪姫』、少し大きくなってから読んだ『不思議の国のアリス』『ヘンゼルとグレーテル』『青い鳥』など。
どの物語も基本的には冒険物語です。
そして、子どもから大人へと成長する通過儀礼のようなお話になっていますね。
家を出て、日常とかけ離れたどこかへ行き、そして帰ってくる。
しかも主人公はより成長して帰ってくる。
これが基本です。
これは、英雄神話の基本構造でもあります。(英雄神話についても詳しく書くと長くなるので、別記事で解説します)
ジブリ映画の『千と千尋の神隠し』なんて、まさにそのものの物語ですよね。このお話には、「行って帰る」間に、「難題を解決する」(たくさんの豚の中から両親が変身した豚を見つけ出す)物語も、「欠如を回復する」(湯ばーばに取られた名前を取り戻す)物語も入っていて、パーフェクトな物語です。
ひとまず初心者が押さえるべき基本は「行って帰る」物語なんだなと憶えておいてください。
すべての物語はここから派生しています。
2.「難題を解決する」物語
ロシア民話の一つ「おおきなかぶ」は誰もが子どものころ読み聞かせてもらった大定番の絵本ですよね。
おじいさん一人では抜けないくらい大きなかぶができました。おばあさんも駆けつけて引っ張るけれど、なかなか抜けない……ではどうするの?という幼い子どもの考える力を引き出しつつ、ファンタジーも交えて、みんなで協力すればどんな困難も解決するよという寓話になっています。
極めて単純な物語なのに、秀逸ですねw
また、アニメの方が有名な「一休さん」もこの文法です。
お殿様の無理難題を、頓知(とんち)を利かせて上手にかわすところに庶民がスカッとする面白味があります。
なぞなぞを物語形式で解いていくのに近い快感ですね。
そして推理小説と呼ばれるものはみんなこのパターンですよね。
ダイナレイはどうしてもポアロより犬神家の人々より名探偵コナンを思い浮かべてしまうのですが……
謎解きはいくつになっても人を惹きつけてやまない楽しいものですよね!
3.「欠如を回復する」物語
あなたが、シェル・シルヴァスタイン「ぼくを探しに」(講談社・1977)という絵本を読んだことがあるなら説明なく理解していただけると思うのですが、90%の円グラフのような「ぼく」が、どこかに落としてきてしまったらしい10%の円グラフの欠片を探しに行くだけ、という物語です。
わかりやすいですよねw
「欠如の回復」は魔法民話に必須の文法です。というか、魔法民話も3つすべての文法を使用して構成されています。
魔法民話といえば、勇者が王様の依頼で拉致されたお姫様を助け出すのが定番です。
この一文だけ見ると「欠如を回復する」文法しか見えませんが、お姫様を助け出すというところで「行って帰る」と「難題を解決する」文法が登場します。
物語の3つの基礎文法まとめ
このように、物語の3つの基礎文法は、多くの人に読み継がれる物語には必須の文法になっています。しかも、どれかひとつというより、2つまたは3つとも使用されているのが普通です。
あなたもぜひストーリーを考える時には、この3つの基礎文法を意識してみてください。
物語の構造とは?魔法民話と英雄神話にも共通
物語の基礎文法についてはわかりましたよね。「行って帰る」「難題を解決」「欠如を回復」する物語。ですがこれは建物でいう基礎、土台部分に過ぎません。
100年くらい前の話ですが、ロシアの民族学者ウラジーミル・プロップという人が、何百というロシアの魔法民話を調べて抽象化していくと、表面上の違いが消えて「同じ」になる水準があるよって気がついたんですね。
ひとつの標準図式(方程式)に還元できると。
それをプロップは「物語の構造」と呼んだんです。
この「構造」が建築でいう木造軸組工法とかツーバイフォーとかいうモノですね。
で、この構造ですが、先ほども文法のところで出てきた古今の英雄神話にも共通の構造があるんですね。
魔法民話 ⇒ 依頼と代行からなる宝探し
英雄神話 ⇒ 異常誕生をともなう貴種流離譚
これまた、「異常誕生」だの「貴種流離譚」だの小難しい言葉が出てきましたが、くわしく説明すると長くなるので別記事にて解説。
ここでは、民話も神話も、それぞれ共通の物語構造を持っているんだなってことだけ頭に入れておいてくださいね。
で、これらの共通の物語構造を構成要素に分解して、方程式にあてはめて、サクッとプロットつくっちゃおう!というのがダイナレイの主張です。
ウソですw 以下に出てくる大塚英志先生の主張です!
方程式にアイテム召喚すればあらすじはサクッとつくれる
方程式にアイテムを召喚する?どういうこと?って感じですよねw
方程式というのは、魔法民話と英雄神話の共通構造から必然的に出てくる標準図式です。
そこに、アイテム= 市販のタロットカードを召喚します!!
ジャジャーン!www
タロットカード!!!
あ、呆れられてる感がハンパないw
――大丈夫です。
これ、マンガ原作者にして評論家の大塚英志先生のお墨付きの方法ですから。
実際に大塚先生も、先生の教え子さんも、この方法でプロットを作成しています。(カードはアレンジされていますが)
ちなみに市販のタロットカードでなければいけないわけではありません。慣れてきたら自作のカードを作ってやってみるのがおすすめです。
ただカード作りに時間をかけるのはもったいないので、既存のカードを使ってサクッとあらすじをつくってしまいましょう!
物語性を刺激されるような絵柄のカードなら何でもいいです。大アルカナ22枚だけで大丈夫です。
この方法の良いところはですね、自分の枠を簡単に超えられるところにあります。
自分の頭の中だけで考えているとストーリーはマンネリ化しがちですが、カードで出たキーワードに強制されることで、思わぬ展開を生み出せたりします。
騙されたと思って一度やってみてくださいな!
1.タロットカード22枚を裏返してシャッフルします。
2.そこからカードを6枚引きます。引いた順に下記の通りに表を向けて並べます。上下逆に出た場合もそのまま置きます。(逆位置といいます)
3.③ ① ② ⑥ (④は②の上に、⑤は②の下に置きます)
※図がないのでわかりにくくてスミマセン!後ほど作成して追加します。
あなたの目の前に、左側だけ飛び出た十字に配置されたカードが並んだはずです。
それぞれの意味は以下の通りです。
①主人公の現在
②主人公の近未来
③主人公の過去
④助っ人
⑤敵
⑥結末
このように、タロットで主人公の運勢を占う感じになります。
あとは、タロットカードに付いてきた解説本と睨めっこしながらリーディングしていくだけです。
カードの意味をくみ取りながら、主人公がどのように行って難題を解決して欠如を回復して成長して帰ってくるかを200~400文字程度のあらすじにしてみましょう。
舞台設定はファンタジーと学園ものの2種類で、ひとつの方程式から2通りのストーリーを作ってみると練習にもなるし面白いですよ。
まずは気軽に。
1本10分程度で、20本くらい作ってみましょう。
20本作り終えた頃には、物語る内燃機関が自分の中に醸造されたのを感じられるはずですよ。
小説の書き方のルールまとめ & おすすめ本というより参考図書
いかがでしたか?
ダイナレイも書いてみてから思いましたが、意外と構成要素が多くて、1回読んだだけでは頭に入らないのじゃないかなと思いました。
ちなみに、ダイナレイは参考図書を何十回と読んでいますが、今回こうして自分の言葉で再構成してみてはじめてすべてを理解しましたw
自分の言葉で表現するって大切ですね。
ですので、あなたも、まずは実践あるのみ!
手を動かしてくださいね。
物語構造(ストーリー)+物語構成(切り口)=物語力(ストーリーテリング)
物語の基礎文法3つ「行って帰る」「難題を解決」「欠如の回復」
物語の構造は共通している
物語の構成要素は6つに絞れる
構成要素の方程式にタロットカードを投入すればあらすじは10分でできる!
もしもこれだけじゃ物足りない、よくわからないよ……という方は、大塚英志先生の本をお読みください。
『物語の体操』大塚英志(朝日文庫・2003)
ダイナレイラボに書いてある100倍は深掘りして解説してくださってますので、ぜひ読んでみてね。ただし、あまり深入りしすぎて戻れなくならないようご注意くださいw
また上記が手に入らないようでしたら、
『ストーリーメーカー』大塚英志(アスキー新書・2008)
もおすすめです。
どちらかというとわかりやすいのは『ストーリーメーカー』の方です。今すぐ小説を書きたいんだ!という方は、手に入れてください。質問に答えるだけでストーリーが自動的にできあがってしまうという魔法のテンプレ(反則技)が手に入りますw
とにもかくにも、まずは書くことに時間と労力を投入してくださいませ。
それでは、まったりダイナレイでした~。